MalletGolf
マレットゴルフについて


人間が初めて使用した道具は、こん棒と石の2つであったといわれています。これが、こん棒と基本的にほとんど変わらない用具を用いるステッィク系打球戯の歴史の始まりかと思われます。
現代のスポーツである野球・ゴルフ・ホッケー・ゲートボール・テニス・卓球もまた、これらの共通した思いから、発祥し分化してきたものと思われます。
さて、マレットゴルフは長野県体育センターで1981年に開発、翌1982年に公表され、市町村関係者に講習会を実施する等普及に努めました。ゲートボールの道具を使って、ゴルフのように穴の中にコロコロと転がしこんでみたらどうだろうか?
手近な場所で、経費をかけずにゴルフのようにスカッとした爽やかさを味わえないだろうか?という創意から考案されたということです。
その後1986年にゲートボールの道具でミニゴルフをしたのが発祥と福井県(福井運動公園)から声があがったようです。
県体育センターでは「どちらでもよいのではないか?」との反応だったようです。やっている人たちがおおらかに楽しめれば良いのではないかということで、そろぞれの県で同じような発想を同じような時期に考えたのではないかと思われます。
そんな中、しが先代社長がこの面白さにはまり、大きな体で思い切り打つ所作の中で木槌ということで割れたり、破片が飛んだりという体験を何度かし、危険性を慮り、自社にある鉄でシャフトを作成しました。それから裏山でグリップを作り楽しむうちに次々と注文が殺到するようになりました。

そして、沢山の人のアドバイスをいただきながら試行錯誤を繰り返して、現在のアルミシャフトも落ち着きました。
当時はアルミはダメ、24cm以下はダメ等用具についても厳しいルールがありました。ダメならば自分達が作った自分達の大会をつくろう!そんな声が上がり「マレットゴルフ友の会」は結成されました。
もちろん、それまでには色々な機関への・働きかけ等紆余曲折がありましたが、初代・田島架裟男会長の基、現在4代目・武内安三郎会長まで、実に167回、21年にわたり、このポリシーを曲げる事無く続けて参りました。(安全・友和・おおらかさ・かっこよさ)
その間松本市で開かれた、県民運動会に採用されたり、各市町村も「生涯スポーツに最適」と受け止め、積極的にコース作りを進め、瞬く間に全県に、さらには県外にも普及していきました。地方発のスポーツがわずか20数年で生涯スポーツのメジャーに発展したのは珍しい例だということです。
そして幸なるかな、友の会の主張は現在、マレットゴルフ界に受け継がれています。
今では県内200を超えるコースと数万人の愛好者が集い、県外でも25都道府県で楽しまれているということです。
【参考文献】
「マレットゴルフについて」県体育センター発行
「マレット発祥と現状」信濃毎日新聞
「マレットゴルフ」インターネット
Playing rules マレットゴルフの競技規則
基本的ルール(ストロークプレイ競技の場合)
◆勝敗の決定
総打数の少ない者を勝者とする。複数のプレイヤーが同打数の場合は、年長者を上位とする。
ただし第1位に同打者数が複数いる時は、プレイオフによって順位を決める。
◆グループリーダーの役割
1、同伴者の確認
2、ホールごとに同伴者の打数の確認
3、ルール・マナーの徹底のうえで、同伴者の融和に努める
4、競技中に発生したトラブルの処置、大会本部への通報
5、最終記録のまとめと報告
◆打順
競技開始前に打順を決める(エントリー順・じゃんけん・抽選等)その大会の指示に従う。
2打以降はボール位置がカップに遠い人から打つ。
カップの1m以内にある場合は連打して打つかマークをしてボールを取り除く。
スタートホール以降は前ホールの打数の少ない人からの打順とす
知っているようで知らないこと。
○ 自打球が傾斜地等での静止時間は、自分が球を打つまでの時間とする。
○ アドレス後にヘッド及び、フェイス面が球に接触した時は、1打とする。
○ ノータッチを原則とする。
○ 動いている球に同伴者又は局外者が接触した時は、球の停止位置を次のプレー位置
○ 誤球は1打付加する。
○ OBの時は予備球を使用しホールアウトまでその球を使う。次のホールで試合球に戻す。戻さなかったときは1打付加する。
○ 不明球は3分以内。OB扱いとし、打った位置より1打付加の打ちなおし。
○ アンプレアブル 競技不可能を宣言し大会規定に従う。
原則はカップに近づかない方向、1ステッィク以内の移動で1打付加。
1ステッィク移動しても打てない時は、球の出た位置からカップに近づけず、1ステッィク以内に移動し2打付加する。
○ カジュアルウォーター
1ステッィク又は1ヘッド移動することができる。大会規定に従う(付加なし)
○ マーク
マークの要求がない限り勝手にマークをしてはならない(1打付加)
進行方向(カップ)にたいして球の真後ろにマークしてから球を取り除く。
自分の順番が来てから球を置きマークを取り除く。
マーカーが他のプレイヤーの邪魔になると要請された時は、1ヘッド移動できる。
○ 浮遊障害物を取り除くことができる。
○ 球の打ち込み
前組の競技者に接触又は競技者を超えたりした時は元打ち(1打付加)
○ 試合球
同径の球を使用。
試合球・予備球・判別できるものとする。
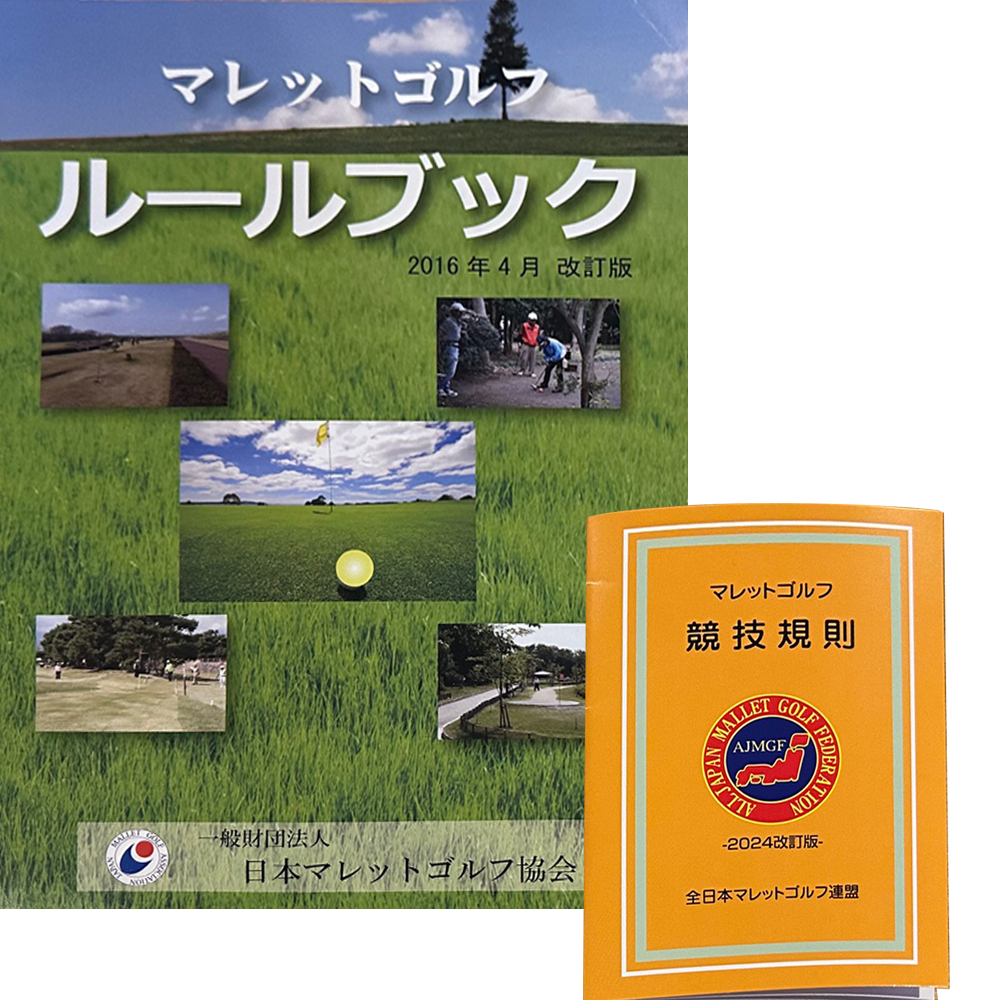
この上で鉛筆マークをクリック - 「見出しテキストの編集」
ルールブック取り扱いしております。
詳しくはお問い合わせください。
Equipment マレットゴルフの用具について
スティック

ヘッドの長さ:120~240mm
フェイス面:45~50Φ
ボール

球:69.5~70.5Φ 190~220g
74.5~75.5Φ 210~240g
